チャート式の歴史,【理科の部屋】の歴史
家の近くの木戸小学校の今日の桜。暖かくなって春本番だ。

今日の朝刊に以下の全面広告。多くの新聞で日曜日は読書欄が設けられ,本の宣伝も多い中,来年の大学受験をターゲットにした参考書類の広告もいくつかあって,もう受験シーズンが始まったことを実感する。
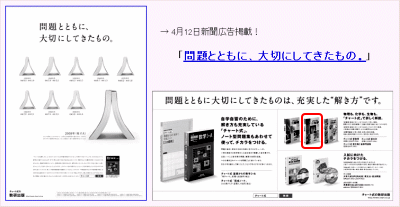
新聞に載っていたのは上記数研出版ページの左側だけだが,右側のバージョンには私が執筆に参加した「新化学」も出ている。これは以前出した「新化学I」と「新化学II」を一緒にしたもので,高校の先生方のリクエストで編集し先月出たばかりである。

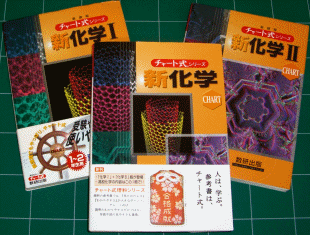
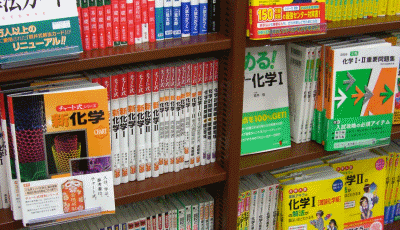
先週ジュンク堂書店新潟店で撮った写真
※執筆参加したものはこのうち4冊(1冊は著者名記載なし)
奥付の著者名には所属は書いていないが,本のどこかには新大学の名前が出ているかも知れない。自分が高校時代にお世話になった参考書の原稿を書くことになるとは夢想だにしていなかったが,学習参考書の著者は通常学校教員と大学人(あるいは大学教員経験者)であり,2009/03/29ほかに記した大学人の「特権」の1つであることを考えると感慨深いものがある。
『チャート式』は以下のブログエントリーにも書いていただいたように歴史ある存在であり,そこに名を連ねられたことは不思議な気もしている。
- 「チャート式」の歴史に学ぶ(私の【理科教師日記】,2009/03/22)
- 参考(同記事で紹介の論文):中村滋・杉山滋郎,『星野華水による"チャート式"の起源とその特徴』,科学史研究,45,209-219(2006)
このブログの著者の楠田さんは,パソコン通信時代にお世話になったNIFTY-Serve(Wikipedia記事参照)に開設されていた電子会議室「理科の部屋」の代表で現在も以下のページを運営してその歴史を繋げ続けている*1。

で,【理科の部屋】についてSPYSEEでネット上での人的関係性を調べてもらった。個人ではないので遠からず消去されるかも知れないけれど。

『つながり』に出ている8人のうち,楠田さんはじめ左巻さん,森さん,青野さんの4人にはオフでお会いしたことがあるということで因縁の深さを改めて感じている。『キーワード』の『分子』をクリックすると私のサイトが出てくるのもうれしい。
【理科の部屋】を出発点としてネットで有用なサイトを立ち上げている方やいろいろなプロジェクトに関わっている方もも多く,クラウドの時代における理科関連コンテンツの重要な部分を占めていると考えられることから,継続することの重要性を再認識しているところである。
なお,インターネットの時代に先立つNIFTY-Serveのフォーラムの位置付けについては以下の本でも触れているので参照されたい。

*1:サイエンスカフェにいがたのスタッフの石坂さんも新潟という地にあって同会議室のスタッフを担当されていた。